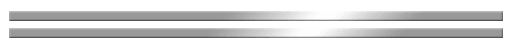
21世紀兵庫づくり懇話会
| 2005年 11月24日木 15.00-17.00 県民会館7階 |
「体験学習は体験を通じて学ぶことです。する→考える→わかる→次のする と[スパイラルに]進んでゆきます」 岩木先生: 「専門知と生活知を縫合する場がワークショップです」 このまえの懇話会で萩原先生がおっしゃった市民知(=合意知)を思い出しました
岩木先生: リハビリのために岩木先生は<ジョハリの窓>をの開かれた領域を広げる訓練をされるのだそうです岩木先生: 「地域人としての再スタートに必要な要素は<自分と出会う><人と出会う><地域とである>です」
①地域福祉計画策定のためのWS (姫路市保健福祉政策課) ②地域で子育て元気アッププロジェクト ③長曽根銀座河原線整備検討WS 坂本一昭 神戸生活創造センター所長からの質問 (1)「地域活動について 地縁組織には自分たちの問題を自分たちで考えるということは期待できない」 (2)「40代くらいから企業内で地域で生きられる訓練をする必要もあるだろう 岩木先生「直接的な講座は地域が作るべき。生活創造センタはそのお膳立てをするのがよいでしょう」 下村さん: 岩木先生「生活知とは生の実感でしょう」 藤井生活創造課長: 鬼本生活創造課主幹: 岩木先生: |
 地域トップページへもどる
地域トップページへもどる2005/11/24 更新
![]()



